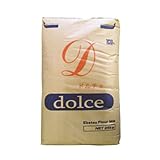納豆や豆乳を買うときはアメリカ産じゃなくて国産大豆のものを選んでいる。
鶏肉を買うときは安くてもブラジル産じゃなくて国産を選んでる。
冷凍ホウレンソウを買うときは中国産じゃなくて国産のを選んでいる。
なんとなく。
そういう人に言いたいことがある。
僕らの食べてる小麦の9割は外国産らしい。
▼小麦でできている食べ物はこんなもの。
パンとか・・
麺とか・・・

パスタ皿 白 K'dep(ケデップ) 白い器シリーズUFOBOWL2枚セット 深 洋食器 丸皿 スープ皿 前菜 食器セット レストラン カフェ
- 出版社/メーカー: K'dep(ケデップ)
- メディア: ホーム&キッチン
- この商品を含むブログを見る
お菓子とか・・・

PINKING 透明シール袋 ビスケットバッグ 自己粘着 お菓子 ケーキ キャンディ収納 小分けラッピング DIY 100個入り
- 出版社/メーカー: PINKING
- メディア: ホーム&キッチン
- この商品を含むブログを見る
これは全部小麦粉からできている。
なんだお前は右に傾いたのかとか無添加云々に傾倒したのかとか、別にそういう話じゃなくて、自分が喰ってる小麦がほぼ外国産だということに素直に驚いたのですよ。
僕らが食べてる小麦はこの国でつくってます
小麦の流通量
1位:アメリカ
2位:カナダ
3位:オーストラリア
僕らが日常的に食べている小麦粉はこの3か国が独占している。
数字でいうと約500万tを輸入に頼り、国内生産は約70万tしかない。
数年スパンで見ても、国産の小麦というのは全体の14~20%をうろうろしてるだけだ。
別に外国産の小麦粉が悪いというわけでは無くて、これには外交上の話とは別に、
ちょっとした理由がある。
例えば、うどんを作るための小麦粉は、ほとんどオーストラリア産である。
しかし、パンを作るための小麦粉はカナダ産が占める。
パン用小麦になぜカナダ産が多いかというと、その品種No.1 Canada Western(通称1CW)という品種がパンを作るのに最適だからだ。
同じくうどんになぜオーストラリア産が使われるかというと、オーストラリア小麦の品種Australian Standard White(以下ASW)がうどん向きの品種だからだ。
料理をする人ならわかると思うけど、小麦粉には強力粉、中力粉、薄力粉と主に3区分あり、それぞれグルテンの量が違う。
細かい説明は省くけど、それぞれ得意分野が違うのだ。
薄力粉はさくさくクッキーとかが得意だし、中力粉はそれなりの粘りがある。強力粉はもっと粘り強いからパンとかピザ生地なんかに向いている。
全てグルテンのなせる業で、含有量が違うから水分が入ったときに、強力粉ほどコシが強くなる。
強力粉(グルテン多い):パン、パスタとかが得意
中力粉(ほどよいグルテン):うどん、強力粉とブレンドしてラーメンもできる
薄力粉(グルテン少ない):クッキー、スポンジケーキが得意
つまり小麦のグルテン量によって、パンに加工しやすい品種、うどんに加工しやすい品種というのが違ってくるのだ。
こだわりのうどん屋で喰ってるこだわりのうどんは、実はカナダ産なのである。
しかもカナダではうどんなんて存在しないんだけど、わざわざ麺がつくりやすいよう品種改良してできたのがASWなのだ。
じゃあ国産の小麦でパンやうどんを作ればいいのでは?と思うかもしれないけど、
そもそもそれができなかった。
日本には強力粉になる小麦品種がほぼな無い(無かった)からだ。
日本の小麦でパンが焼けない・・・
パン作りに向くのは強力粉。
ところが強力粉の小麦品種がほぼ無かった。
日本の小麦でパンを焼きたくても、パンを焼けるような小麦品種がそもそも存在しなかったわけだ。(全くなかったわけでは無いけど、病気に弱かったりして普及しなかった)
もちろん小麦自体の栽培はしていたけど、あまり品質の良いものではなかった。
実際、30年ほど前は国産小麦を持て余している時代だった。という事を北海道の物流会社の人から聞いたことがある。小麦は国の管理だから、使う使わないにかかわらず食品会社に「これだけ使うように」と量を割り当てられていた。しかしうどんに加工しても色は悪いし、パンも焼けないし、ってことで食品会社としてはあんまり欲しくない‥‥と扱いに困った企業もあるらしい。
そういう不遇の時代が続いたんだけど、品種改良によって最近の小麦はちょっと違う。主に北海道で。
北海道の小麦がんばる
長くそういう時代が続いたけども、日本でも品種改良が進んでいろんな小麦が誕生した。
本州の小麦はわからないが、北海道に限って小麦品種の変遷をたどってみる。
ちなみに北海道は日本の小麦の70%を生産している。
ホロシリコムギ:1970年代に活躍した。この名前を知っている人はあまりいない。
↓
チホクコムギ:1980年代に活躍した。雨にも雪にも弱かった。
↓
ホクシン:1994年くらいにでてきたつ。チホクコムギより病気に強く味もよくなった。
でもうどんにすると、黄色っぽくなって見栄えが良くなかった。
↓
きたほなみ:2006年くらいにでた希望の星。この辺りから北海道小麦の評価が上がってきた。
ホクシンより色が白いうどんを作れるようになった。食感もASWと同等、互角に戦えると判定された。
というわけで今ではうどうんに適する「きたほなみ」、強力粉でパンも焼ける「ゆめちから」、「春よ恋」など、外国産に品質が劣らない品種が北海道からたくさん登場してきた。
品種の変遷について簡単に書いたけど、品種改良は新しい品種を作るのに15年もかかるそうである。15年‥‥ 長い。
こうやって品種が変わってきたのはここ最近の話だ。
スーパーでも北海道産小麦を使った食品が見られるようになったし、本州の人でもパン作りが趣味なら北海道小麦の品種を結構聞いたことあるんじゃないかと思う。
時代は変わった。


江別市は「江別製粉」という製粉所もあり、町を挙げて小麦の町宣言をしている。
地方都市の割に市内にパン屋がめちゃ多い。

留萌市では、デュラム小麦に近い小麦を原料として「ルルロッソ」シリーズを発売中。
ルルロッソの正体は北海259号という小麦なんだけど、癖が強すぎて普及用品種になれなかったいわくつきの品種。だからこの小麦を栽培しても、農家に国からの助成金は出ない。
ところがパスタにすると今までの国産小麦にはない、まるでデュラム小麦みたいだ!という利点がある。それを生かそうと、生産者や製麺会社、製粉会社が協力してめでたく製品になった良い話。
*
別に外国産の小麦を批判するつもりはないし、小麦の味がわかる人にとっては海外産が良いよって人も居ると思う。
昔と違って、北海道産小麦っていう選択肢が増えたのは料理する側食べる側にとってはいいんじゃないか。
僕らが食べたら生産量も増えると思うし、ここがダメだとか、こういう味がいいっていう意見が15年後に生まれる新しい小麦に繋がる気がする。
まあ今の政治じゃ日本の農業もどうなっちゃうかわかんないけど‥。